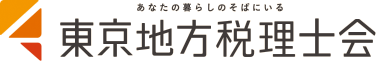Q&A教えて税理士さん®

酒税法上の酒類とは<令和元年12月>

年末になり、お酒を飲む機会も増えてきました。そもそも酒税法上の酒類とは、どんなものですか?

酒税法上のお酒とは大まかに言うと、アルコール分が1度以上の飲料です。薄めてアルコール分1度以上の飲料にできるものや、溶かしてアルコール分1度以上の飲料にできる粉末状のものも含みます。『アルコール分1度以上』で『飲料』という両方の条件が必要で、どちらかを満たさない場合にはお酒とはなりません。

粉末状のものって?

お菓子の原料などに使われる『粉末酒』と呼ばれる粉状のお酒です。粉末酒そのものは溶かして飲料にできるので、お酒になります。一方、粉末酒を使ったお菓子は飲料ではないので、基本的にお酒には当たりません。

薬局等で販売されているドリンク剤などには、アルコール分1度以上のものもあると聞いたことがあります。

ドリンク剤などのうち、『容量が少ないもの等については強いてお酒には分類しない』という通達があります。そのため、これらも酒類には該当しません。

ビールや発泡酒は税率が違うそうですね?

350ml缶当たり、酒税はビール77円、発泡酒47円、第三のビールは28円です。税率の差によって第三のビールなどは安価で商品化されていますが、2026年10月までに一律54.25円に統一されます。
(東京地方税理士会・金子 浩也)
| [←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→] |