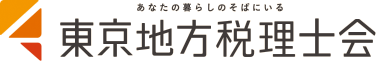今年の法人税改正は、成長志向に重点を置いたと言われています。つまり、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、より広く負担を分かち合い、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することがその趣旨のようです。
改正事項はたくさんありますが、常識として知っておくべき重要なポイントは以下の3点です。
- ①まず、税率の改正です。資本金1億円以下の中小の普通法人などで所得金額年800万円超の部分の税率は、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます(平成27年4月1日以後開始事業年度より)。所得金額年800万円以下の部分の現行税率15%(いわゆる“中小法人等の軽減税率の特例措置”)については、景気動向に配慮し、適用期限が2年延長されました(平成27年4月1日以後開始事業年度より)。
- ②次に、法人が保有する他の法人の持ち株による受取配当等の益金不算入割合は以下のように改正されました。法人の持株比率が100%の場合では、改正後も同じく受取配当等益金不算入割合は100%であり、かつ負債利子控除もありません。法人の持株比率が3分の1超100%未満の場合も受取配当等益金不算入割合は100%ですが、負債利子控除はあります。
次に、持株比率が5%超で3分の1以下の場合では受取配当等益金不算入割合は50%ですが、負債利子控除は廃止されました。また、持株比率が5%以下の場合の受取配当等益金不算入割合は20%となり、同様に負債利子控除は廃止されました。
むずかしいかも知れませんが、負債利子控除とは、銀行借入金(負債)などで株式を購入する場合、負債利子は損金算入でき、株式の配当金も益金不算入とすると二重非課税となり、それを避けるため、負債利子相当額は益金とみなす(つまり益金不算入としない)制度です。
- ③最後に、欠損金の繰越期間の改正です。現行の9年から10年に延長(平成29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金について適用)されました。同時に帳簿書類の保存期間、欠損金額にかかる更正の請求期間及び更正の期間制限も、現行の9年から10年に延長されました。これも注意しましょう。
|